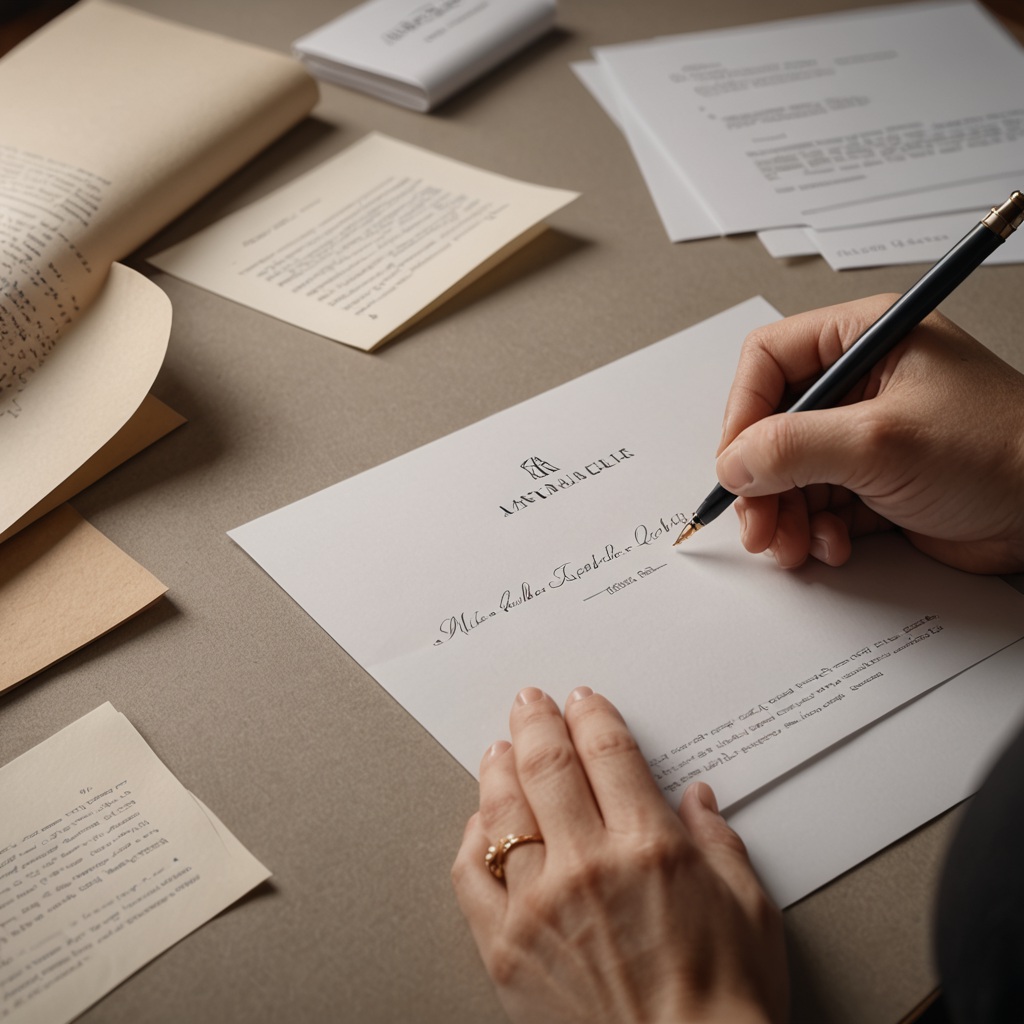«当記事には、広告を含む可能性があります。»
こんにちは!ブログにお越しいただきありがとうございます😊
小学6年生の息子(さめくん)と小学5年生の娘(くまちゃん)を育てている、ごく普通の40代主婦です。
毎日バタバタと過ぎていく中で、子どもたちとのコミュニケーション、特に思春期に片足を突っ込んでいる息子のことで悩むことが増えてきました。「何度言っても聞いてくれない」「同じことを何度も言わないといけない」…共感してくれるママさん、きっといらっしゃいますよね?
特に、今年は息子にとって大切な受験の年。親として、色々なことを伝えたい、応援したいという気持ちはあるのですが、言葉で伝えても、なんだかスッと心に届いていないような気がするんです。
「宿題したの?」「歯磨きしたの?」「早く寝る準備しなさい!」
口を開けば、そんな言葉ばかり。息子も「はいはい」とは言うものの、行動に移るまでには時間がかかったり、結局やらなかったり…。私も、ついつい感情的に叱ってしまい、後で自己嫌悪に陥ることも少なくありません。
そんな時、「もしかしたら、言葉で直接伝える以外の方法が良いのかもしれない」と思い始めたんです。そして、ふと頭に浮かんだのが「手紙」という手段でした。
なぜ今、「手紙」で伝えたいと思ったのか
デジタル化が進んだ現代において、手紙を書く機会はめっきり減ってしまいましたよね。でも、だからこそ、手書きの手紙には特別な力があるのではないかと感じています。
じっくり考えて伝えることができる魔法
口頭で話す場合、どうしてもその場の感情に流されてしまったり、言葉足らずになってしまったりすることがあります。特に、子どもを叱る場面では、冷静さを保つのが難しいと感じることも…。
でも、手紙であれば、伝えたいことをじっくりと考え、言葉を選ぶことができます。頭の中で整理しながら書くことで、感情的な言葉を避け、冷静に、そして丁寧に自分の気持ちを伝えることができるはずです。これは、私自身が後悔するような叱り方を減らすための、良いストッパーになるかもしれません。
形として残る、ということの重み
手紙は、書いた時の気持ちや状況をそのまま形として残すことができます。口頭で伝えたことは、どんなに大切なことであっても、時間の経過とともにどうしても薄れていってしまいます。
もちろん、手紙を渡したからといって、必ずしも子どもが大切に保管してくれるとは限りません。もしかしたら、すぐにどこかにいってしまうかもしれません。それでも、手紙という「形」にして渡すことに意味があると思うんです。
いつか、ふとした瞬間に見返して、親の気持ちを改めて感じてくれることがあるかもしれません。人生の大きな節目を迎えた時、悩んだ時に、手紙を読み返すことで、少しでも勇気づけられることがあるかもしれない。そう思うと、やっぱり手紙という形に残しておきたいのです。
気持ちがより伝わりやすい温もり
直接言葉で伝えるのは、少し照れくさいことってありますよね。「頑張っているね」とか「いつもありがとう」といった感謝の気持ち、「あなたのことが大切だよ」という愛情表現。改まって言うのは、なんだか気恥ずかしい…。
でも、手紙という形にすることで、素直な気持ちを表現しやすくなるのではないでしょうか。文字を通して、私の温かい気持ちが、きっと息子や娘にも伝わってくれると信じています。書いているうちに、私自身の気持ちも整理されて、より優しい気持ちになれるような気もします。
考える時間を与えるという優しさ
手紙は、受け取った側が自分のペースで読み進めることができます。特に、少し難しい話や、感情的な内容が含まれている場合、すぐに言葉で返答を求めるのではなく、じっくりと考える時間を与えることは、とても大切だと思います。
息子も、受験という大きなプレッシャーの中で、色々なことを考えているはずです。私の気持ちを手紙で伝えることで、彼が自分のペースでそれを受け止め、考える時間を持つことができるかもしれません。
特別なコミュニケーションという宝物
手書きの手紙は、メールやメッセージアプリとは違う、特別な温もりがありますよね。デジタルなコミュニケーションが主流になった今だからこそ、手書きの手紙は、子どもにとって新鮮で、心に残るものになるのではないでしょうか。
「お母さんが、自分のためにわざわざ時間をかけて書いてくれたんだ」という気持ちは、きっと親子の絆をより一層深めてくれるはずです。
文字に触れる、ということの大切さ
最近は、学校の連絡事項もほとんどがデジタル化されています。子どもたちが手書きの文字に触れる機会は、以前に比べて減っているかもしれません。
手紙を書くことは、文字の美しさや、書くことの楽しさを伝える良い機会になるかもしれません。もしかしたら、これをきっかけに、息子や娘自身が手紙を書くことに興味を持ってくれるかもしれませんね。
やっぱり、無機質なデジタル文字よりも、手書きの文字には、書き手の温もりや気持ちが伝わる気がします。
手紙を書くことのちょっぴり気になるデメリット
もちろん、手紙にはメリットばかりではありません。正直なところ、「面倒くさいな」「時間がかかるな」と感じてしまうこともあります。
特に、忙しい毎日を送っていると、まとまった時間を取って手紙を書くのは、なかなかハードルが高いかもしれません。
でも、それでも、子どもたちに伝えたい大切なことがある時、手紙という手段は、そのデメリットを上回る価値があるのではないかと私は思っています。
手紙の長さはどのくらいがベスト?
手紙を書く上で悩むのが、その長さですよね。長すぎる手紙は、読む子供にとっても負担になってしまいますし、書く方も疲れてしまいます。かといって、短すぎると、伝えたいことが十分に伝えられないかもしれません。
以前、教育に関する本で読んだのですが、小学生高学年のお子さんが集中して読める文章の目安は、3分程度と言われています。もちろん、個人差や文章の内容によっても変わってきますが、3分で読める文字数…大体1000字くらいを目安にするのが良いのかもしれません。
もちろん、これはあくまで目安なので、伝えたい内容に合わせて、長さを調整するのが一番大切ですよね。
まとめ~言葉が届かない時こそ、手紙で心をつなげよう
今回は、私が最近考えている「手紙で子どもに気持ちを伝える」ということについて、色々と語らせていただきました。
言葉で伝わらないと感じる時、何度も同じことを繰り返してしまう時、手紙というアナログな方法が、意外なほど効果を発揮してくれるかもしれません。
手間や時間はかかるかもしれませんが、その分、子どもに伝わる温もりや深さは、きっと格別なはずです。
私も、近いうちに、息子と娘に宛てて、心を込めた手紙を書いてみようと思っています。どんな反応をしてくれるかな?少しドキドキしますが、楽しみでもあります。
同じように、お子さんとのコミュニケーションで悩んでいるママさん、ぜひ一度、「手紙」という魔法を試してみてはいかがでしょうか?
これからもこのブログでは、中学受験を目指す中での体験記事、他には過去の子どもたちへの教育でこんなことを試して、こんな効果がでたとか失敗したとかなどの体験記事、今まで読んだ教育に関するとても参考になった本の紹介記事などを書いていきたいと思っています。
同じように中学受験を目指すご家族や幼稚園や小学生低学年の子供を持つ親御さんにぜひ読んでもらいたいです。
これからもどうぞよろしくおねがいします。